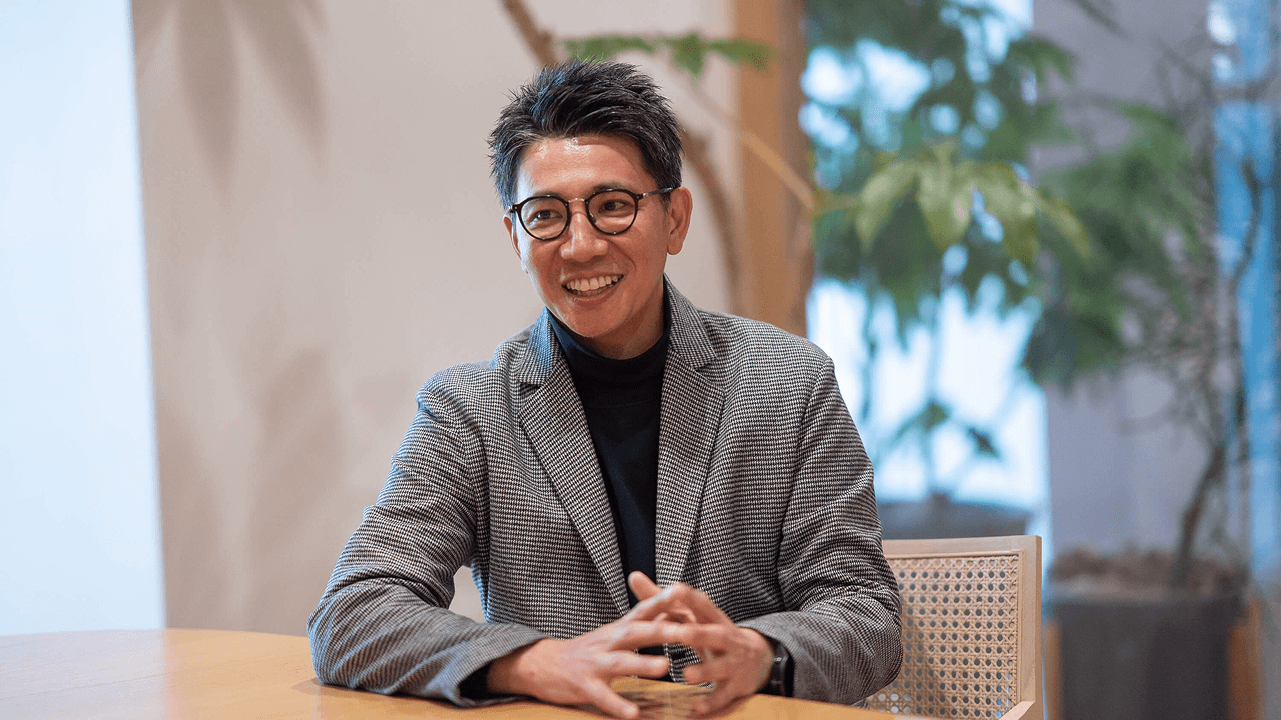2025.03.21
【特別対談企画 VOL. 24】商売の本質を貫き、時代を先読みする——三和エステート田代副社長の挑戦
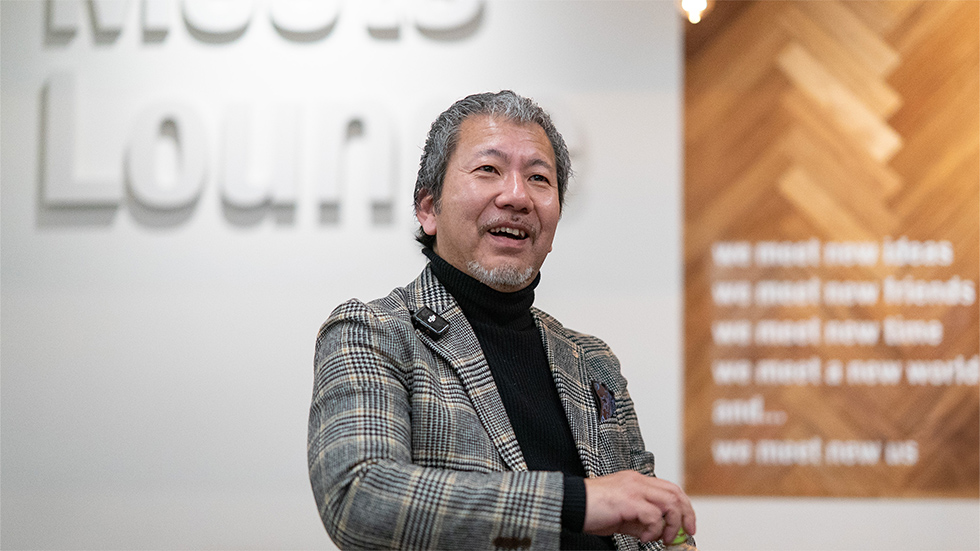
「不動産管理会社のいまを知る」をテーマに、業界をリードするゲストを迎える連載企画。第24回は、不動産資産管理会社として総合的に不動産事業を営む三和エステート株式会社 代表取締役副社長・田代雅博氏にお話を伺いました。
19歳で目の当たりにした不動産バブル、20代での起業と挫折、ゼロからの再出発——。多様な経験を経て、第二創業期の三和エステートに参画した田代氏は、同社の不動産事業を牽引し、企業文化を築いてきました。「負けない経営」を掲げ、時代の変化を先読みしながら、持続可能な成長を目指す田代氏の挑戦に迫ります。
ゲストプロフィール
三和エステート株式会社 代表取締役副社長 田代 雅博氏
19歳で不動産業に携わりながら、20歳で異業種での起業を経験。平成バブル崩壊で廃業を余儀なくされ、その後、地場不動産会社で競売や買取再販を習得。28歳で三和エステートに参画し、第二創業期を支える。2010年のグループ再編を機に、グループホールディングス執行役員、三和エステート専務取締役などを歴任し、2022年より現職。不動産資産管理会社として「人生に、経営力」を掲げ、資産管理、コンサルティング、不動産クラウドファンディングまでを展開。各事業価値をつなぐバリューチェーン構築に注力している。
目錄
19歳で不動産バブルの最前線へ
ーーまずは、田代副社長について教えてください。
北九州市で生まれて、福岡市で育ちました。父は旧国鉄の職員、いわゆる公務員でしたが、私の周りには商売を営む家庭が多かったんです。食堂とか酒屋とかね。そうした環境の中で自然と「商売って面白い」と感じるようになりました。
小学生の頃は、友達と一緒に「どうやったらお金を作れるか」を考えるのが日常でした。プラモデルがほしかったから、酒屋の息子の家にあったリヤカーに皆で古本を積んで、近くの古本屋に売りに行ったりして。当時はただプラモデルを買いたい一心でしたが、あれが今の原点だったのかもしれません。
ーーその頃から、単純にお金をもらうのではなく、仕組みを自分で生み出すことを考えていたのですね。社会人としては、どのようなキャリアを歩まれましたか。
19歳の時にとある不動産会社に入社し、社長の鞄持ちと運転手を朝から晩まで務めていました。思い返せば、社長はちょうど今の私くらいの年齢でした。
その頃は、バブル真っ只中。FAX一枚で何十億もの土地が動くような時代でした。「すごい世界だな」と圧倒されましたが、次第に「こんなことがずっと続くはずがない」とも思っていました。
ーーまさに不動産バブルが弾けるタイミングを間近で見られていたんですね。
商談や会食にも同行させてもらっていたので、周囲の経営者たちが次々に姿を消していくのを目の当たりにしました。日を追うごとに見かける顔ぶれが変わっていくんです。「これは大変なことが起きている」と肌で感じましたし、19歳の私にとって、社会と経済の現実を身をもって知る貴重な経験でした。
起業と失敗、プレイヤーとして再び不動産業界へ
ーーその後も今に至るまで不動産業界にいらしたのでしょうか。
いえ。実は、20歳の時に友人と起業しているんです。飲食店向けに短時間のアルバイトスタッフを派遣する事業でした。当時、求人広告を出すと、学生やOLの方がたくさん応募してくれて。
ーー今でいう「スキマバイト」のマッチングサービスですよね。世の中の需要を見抜く力があったんですね。
いや、そんな大層なものではないです。ただ、鞄持ち時代に色々なお店に同席していたので、ニーズは理解していました。「人が足りなくて困っている店がある」「短時間で稼ぎたい人がいる」、その二つを繋いだんですね。

その後、好調だったので別の事業もスタートさせたのですが、最終的には資金管理の難しさから大きな負債を抱えてしまって。20代前半でゼロからのスタートを余儀なくされ、再び不動産業に戻ることになりました。
正直に言えば、当時は不動産業に特別な思い入れがあったわけではありません。「お金を稼ぐ手段として何ができるか」を考えた結果、不動産が選択肢として残ったという感じでしたね。一方で、以前のような鞄持ちではなく、今度はプレイヤーとして仕事を覚えようと強く決意していました。
人の人生に深く関わる不動産業の責任の重さ
ーー具体的にはどんな仕事をされていたのですか。
メインは買取の再販です。当時の不動産売買は債務整理が中心。つまり、住宅を手放さざるを得ない人と、夢を持って新しく住宅を購入しようとする人の間に立つ仕事です。
ーー立場が変わると、見える景色も違ったのでは。
まったく違いましたね。売主の方は、仕事を失ったり会社が倒産したりして、やむを得ず家を手放す人がほとんど。一方で、買主の方は、新しい生活をスタートさせようと希望に満ちています。その両者を繋いでいく中で、世の中の厳しさや、人の人生に深く関わる仕事の責任の重さを実感しました。これは、私の人生の中でも最も深い学びの一つでした。
ーー異なる状況にいる両者の思いを汲みながら取引を成立させるために、どのような工夫をされていましたか。
共通しているのは、売主も買主も「これから」のことを考えているという点です。だからこそ、売主の方が抱える「これから」の不安を取り除くことが、スムーズな取引への架け橋になると考えました。
家を売ることは終わりではなく、新しい人生の始まりでもあります。その立脚点から、売主の方の売却後の生活設計について一緒に考えることもありました。私自身がまだ若造で経験も浅かったのですが、知り合いの社長に連絡して「この方を雇えないか」と紹介することもありました。
ーー単なる売買仲介ではなく、人生の再建をサポートするような仕事ですね。ゼロになったからこそ、新しいプラスを作ることができる。田代副社長だからこそ到達できた視点だと思います。
第二創業期の三和エステートとの出会い
ーーその後、三和エステートに入社されたんですよね。当時はまだ不動産業としての規模は小さく、ある意味で第二創業のような形だったと聞いています。田代副社長が事業を拡大していくまでの経緯を教えてください。
創業間もない頃に、先代の会長とご縁があってお話しする機会がありました。その流れで入社することになったのですが、7人のスタッフに対して事務所はわずか5坪(笑)。今から30年前、1996年のことです。
会長から言われたことは、「いい会社にしてくれ」「損失をなくして内部留保を確保してくれ」——この二つだけ。会長は本当に口を出さない方でした。お金の面では支援してくれましたが、経営の細かい部分には一切干渉しなかった。だからこそ、自分で考え、行動しなければならない環境でした。
ーー「いい会社にする」って、シンプルでいて至極難しいミッションですよね。どこから取り組まれたのでしょうか。
まず、組織を変えることが先決だと感じました。当時、社員の中には第二の就職先として来られた60代の方や、別のグループから転籍してきたスタッフもいました。私が最年少でしたが、仕事をする上で年齢は関係ありません。事業責任者として率先して環境を変え、明確な方向性を決めていきました。
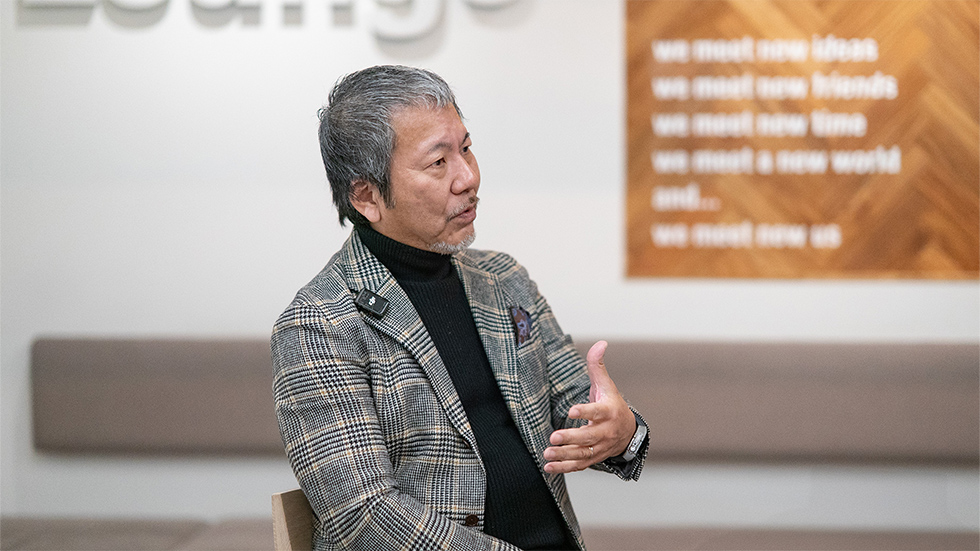
事業としては、私が最も経験を積んでいた売買の分野から始めました。「三和エステートっていい会社だよね」と言われるための第一歩として、まずは「ご飯を食べられる会社」にしようと。とにかく利益を上げ、会社の基盤を安定させることが最優先でした。売買を軸に事業を組み立てながら、次第に賃貸管理や開発へとシフトしていく流れを作っていきました。
ーーまさに、基盤づくりからのスタートだったんですね。
ストック型ビジネスへの成長戦略
ーー現在は管理業としての規模も大きくなっていますね。開発から管理まで、一連のバリューチェーンを手掛けられていますが、どのように事業のシフトを進めていかれたのでしょうか。
最初の頃は、ひたすら売買を伸ばし、業績を安定させることを考えていました。利益をしっかり確保し、会社の基盤を作り、まずは「三和エステート」の名前を業界に広めることが第一でした。
ただ、その頃から「将来的には賃貸管理が強みになる」と考えていました。30年前の当時は賃貸管理業はそこまでメジャーではありませんでしたが、積み上げ型のストックビジネスとしての魅力を感じていましたね。その後、M&Aを活用して仲介機能を強化し、徐々に管理事業に軸足を移していきました。
ーー売買、開発、賃貸、管理においてはそれぞれ異なるスキルが求められますが、人員面においてはどのように事業の変遷を乗り越えてこられたのでしょうか。
シンプルに言うと、自分より優秀な人に働いてもらうことです。それぞれの分野で優れたスキルを持ったメンバーが集まってくれているので、私は彼らをまとめる役割に徹するようにしました。スキルという観点では、弊社のメンバーは私よりも全然優秀ですから。
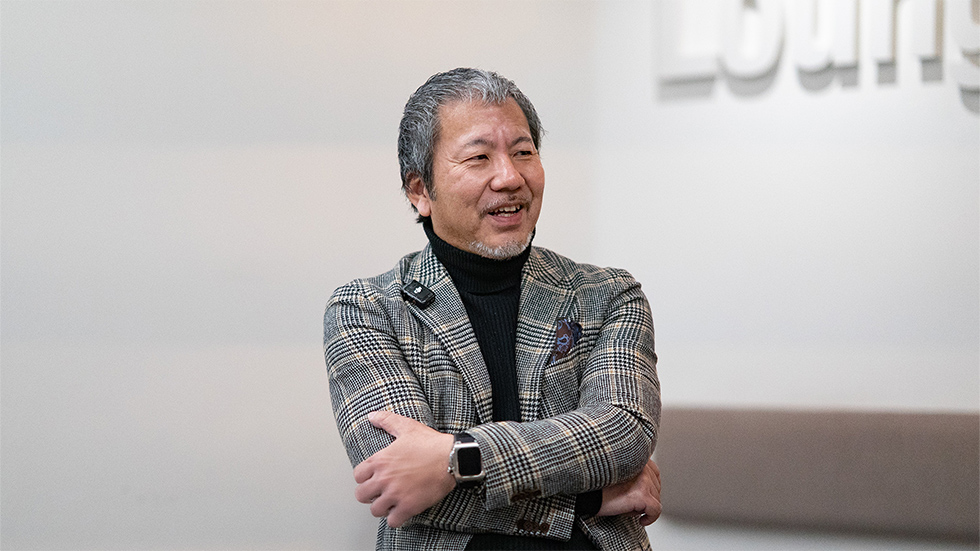
ーーその考え方ができるリーダーはなかなかいませんよね。
いえいえ、私は学歴もないし、専門的なスキルも正直、皆の方が上。ただ、彼らが持っていない「経験」や「視点」はある。だからこそ、組織全体のバランスを取りながら、時代の変化や成長の方向性を見極めることが私の役割だと考えています。
また、これは先代からの影響もあると思っています。先代は「金は出すが口は出さない」というスタンスを貫いていました。経営者として、いろいろ言いたいことはあったはずですが、あえて言わない。それがどれだけ難しいことか、40代を超えた頃からようやくわかってきましたね。
ーー「言えない」のではなく「言わない」。それは、組織を成長させる上で重要な要素ですね。
本当にそうです。リーダーがすべてをコントロールしようとすると、組織の成長が止まるんです。だからこそ、信頼できる人材に任せるべきところは任せ、自分は全体を見守る。そうすることで、会社全体が自然と成長していくんじゃないかと思っています。
従業員が誇れる会社をつくる
ーー三和エステートは従業員の定着率が高く、ジュニアの頃から成長したメンバーが執行役員になるケースも多いと聞きます。創業メンバーと若いメンバーのバランスもよく、会社全体に家族的な温かみがありながらビジネスとしての厳しさも併せ持っている。これは、田代副社長の「従業員に任せていく組織作り」によるところが大きいのではないでしょうか。
いえ、私が組織を作ったというより、皆が築いてきた結果だと思っています。ただ、一人ひとりの人生と向き合うことは常に意識してきました。結婚、出産、家の購入といった彼らの人生の節目を見届ける中で、安心して働ける環境を作る責任を感じるんです。

例えば、従業員の中には社内結婚をして三和エステートの物件に住み、子供を会社の保育園に預けている人もいる。職場が単なる仕事の場ではなく、生活や人生の一部になっているのを見ると、「もっといい環境を作らなければ」と強く思います。
そうした考えのもと、当社では社員一人ひとりが会社の方向性や財務の状況を正しく理解し、同じ視座で動けるようにするため、情報共有を徹底しています。年度初めの経営計画発表会は30年間毎年継続しており、さらに四半期報告会を実施、四半期ごとの振り返りと方針確認を全従業員と行っています。また、月次決算におけるBSやPLの内容も、責任者にはすべて開示しています。「良いこと」も「そうでないこと」も、目標も現実も、すべて共有する。不動産競売や債務整理に携わった経験が、今の経営スタイルにつながっています。
環境を変え、未来へ進む——オフィス移転とロゴ刷新
ーーそうした組織作りの一環として、近年ではオフィス環境の見直しにも積極的に取り組まれていますね。
お客様のお部屋探しのスタイルが、スマホやPCで検索し、現地で待ち合わせて内覧する形に変化したため、駅前にあった賃貸ショップ3店舗の統廃合を行い、本社2階へ移転しました。これにより、店舗コストをWebサイトやSNSでの物件紹介や情報発信へとシフトさせ、本社の賃貸管理課との連携を強化しています。
また、賃貸仲介の経験者が資産コンサルティングや売買業務へスムーズにジョブローテーションできる仕組みも整えました。社内の成長機会を広げ、従業員が「ここで長く働きたい」と思える環境作りを意識しています。その結果、現在、資産コンサルティング部の投資不動産の売買メンバーの80%は、賃貸仲介・賃貸管理の出身者です。賃貸市場や管理業務を深く理解しているため、売買を通じた賃貸経営のアドバイスがより実践的なものとなり、オーナー様からの評価にもつながっています。
ーーオフィス移転が、単なるコスト削減や効率化に留まらず、働きやすさや成長機会の創出にもつながっているのですね。また、30周年を迎えたタイミングでロゴも刷新されましたね。
新しいロゴは広報メンバーによる起案・デザインで、「青い日の丸」がシンボルになっています。赤い炎よりも温度が高い青に、コーポレートカラーである青を掛け合わせ、「安心」「情熱」「共存」の意味を込めました。「信頼を守りながら新たな価値を生み出し、変革を恐れず未来へ進む」という私たちの姿勢を示しています。
会社は時代とともに進化していくものですが、一番大事なのは「働く人がどう感じるか」。創業30周年を迎えた節目でロゴを刷新したのも、社員と共に歩み続ける企業でありたいという想いがあったからです。

ーーロゴの刷新も、単なるデザイン変更ではなく、三和エステートがこれから目指す未来を表現したものなんですね。まさに、企業の進化と社員の成長を両立させる「社員が誇れる会社作り」ですね。
好調な福岡市場に甘えず、「負けない経営」を追求
ーーお客様からのご依頼に基づいて関東にも進出され、虎ノ門に東京オフィスを構えられましたよね。管理受託総数10,200戸のうち、関東圏では約20%に当たる1,700戸の物件を管理されていると伺いました。九州のみならず、関東でも管理の規模を拡大されていらっしゃいますが、今後はどんなチャレンジをされていくのでしょうか。また、福岡の市場については、どのように見ていますか。
現在の当社の事業の中心には、資産管理があります。売買も賃貸も管理も、すべてはお客様の不動産資産を活かし、守るための手段です。人口や社会、経済の構造が大きく変化している今、売買コンサルティング、新築事業、資産ソリューションなどを通じて、オーナー様が抱えるさまざまな課題を解決すること、人生の目的を果たすためのお手伝いをさせていただくことを軸にしています。
福岡は全国的に見ても注目される都市ですが、私自身は楽観視していません。確かに人口は増えているものの、その多くは九州の他県からの流入です。福岡市で生まれ育った若年層は減少傾向にあり、九州全体でも若い世代の減少が進んでいます。この流れが続けば、今は好調でも、5年後、10年後には市場環境が大きく変わる可能性があります。現状に甘んじることなく、長期的な視点で経営戦略を立てることが重要だと考えています。
ーー確かに、国内で自然増している都市は減少傾向にありますし、福岡も例外ではないかもしれませんね。インバウンド需要や土地の高騰、外資の参入もありますが、その中で田代副社長が意識していることは何でしょうか。
これまでは「市場で勝たなければならない」と考えていましたが、今は「負けない経営」を意識しています。短期的な利益を追うのではなく、3年後、5年後を見据え、リスクを抑えながら持続可能な事業体制を作っていくことが最優先です。そのために、社内体制の強化や基盤の見直しを進めています。
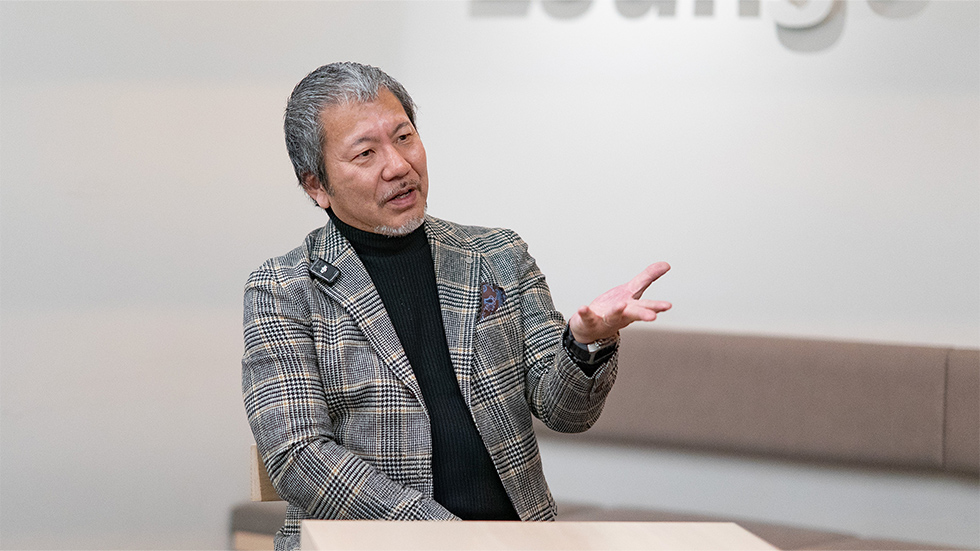
ーー事業の成長だけでなく、リスク管理にも重点を置かれているのですね。
はい。福岡の市場が今後どう変化するかは不透明であり、さらなる環境変化が予測されます。今後、これらに柔軟に対応できるような経営基盤を作っていくことが課題です。また、私たちはこの変化を脅威ではなく機会と捉えて、私たちが変化を起こす側でありたいと考えています。
ーーこれからの時代の変化に合わせてどのようなチャンスを掴んでいくのか、今後も楽しみにしています。
関わる全ての人の「居場所」に
ーー最後に、メッセージをお願いします。
お客様へのサービスを追求するのは当然ですが、まずは共に働いてくれている従業員の皆さん、そして取引先のパートナー様に「三和エステートと関わってよかった」と思ってもらうことが大切だと考えています。それがあって初めて、お客様に最良のサービスを提供できると思っています。
支払いについては、1日たりとも遅れたことはありません。受け取るものについては片目を瞑りますが、支払うべきものが遅れることは絶対にあってはいけない。その信頼を守ることが、長く事業を続ける上での基本だと考えています。
従業員に対しては、それぞれの家庭があり、そこが大切な居場所であることを尊重しています。そして、仕事をする場としての三和エステートもまた、もう一つの「居場所」であってほしい。仕事は人生の一部ですが、全てではありません。だからこそ、プライベートを大切にしながら、仕事にも真剣に向き合ってほしいと思っています。
言葉は少し荒っぽいですが、仕事を「利用する」くらいの気持ちでいい。自分の夢や目標を持ち、それを叶えるために三和エステートという場を活用してほしい。右足はプライベートに、左足は仕事に置いて、バランスを取りながら、どちらも充実させていくことが大切です。
ーー非常に大切な言葉ですね。「居場所」という考え方が、田代さんの経営の根幹にあることが伝わってきます。本日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。

インタビュアー:WealthPark Founder & CEO 川田 隆太
田代副社長のおすすめ
インタビューの締めくくりに、田代副社長から福岡市の”おすすめのお店”を教えていただきました。多忙を極める田代副社長の日々の活力やリラックスの源になっている、とっておきの4店をご紹介します。
三和エステート株式会社
代表取締役副社長 田代 雅博氏
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-6-9 三和ビル3F
会社ホームページ: https://www.sanwa-estate.com/
<本件に関するお問い合わせ先>
三和エステート株式会社
Contact: お問い合わせフォーム窓口
WealthPark株式会社 広報担当
Mail: pr@wealth-park.com